「ぬくい」芸術家はいない。
- Yuma Dobashi Official

- 2018年5月16日
- 読了時間: 6分
まず、「ぬくい」ってなんですか?って話なんですが、
最近知った表現で、「ぬくい」とは人を形容する関西弁らしい。
「ほら、あいつ、ぬくいやんか。」みたいに言うんでしょう。
まず褒め言葉ではなさそうなことが伝わってきて嫌な感じなんですが、
「ぬくい」っていうのは、ニュアンスでしか説明できないけど
危機管理能力がなかったり、鈍感だったりする人を表します。平和ボケとも言えます。
馬鹿とかとはすこし違うんですね。「ぬくい」の反対語は何になるでしょう。
「鋭い」「シャープ」「鋭敏」「知恵者」、、なんだろう。
とにかく心身とも冴え渡ってる人のことですね。
まず、基本的に我々「大衆」というのは「ぬくい」です。
この世界はごくごく一部の人間に統治・支配されることで成り立っているわけですが、
「だからなに?」と思うほどに「平和ボケ」で「従順」なんです。
PeopleをもじってSheeple(羊=Sheep)なんて言葉もあるくらいです。
楽しければいいし、自分たちの周辺が平和であれば、なんとか幸せだと感じることができます。防衛本能の働きでしょうか。
原発で未だに数十万人が困っていても、オリンピックに諸手を挙げることができます。
両手下げとけまで言うと敵だらけになりそうなので、片手くらいにしておこうと思います。
宮沢賢治は「農民芸術概論綱要」という論文でこう言っていてガツンとやられたのを覚えています。以下は一部抜粋。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。 自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する。 この方向は古い聖者の踏みまた教へた道ではないか。 新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある。 正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである。 われらは世界のまことの幸福を索ねよう。」
世界全体が幸福にならないと個人の幸福はないって、そう言ってます。
本当にそうだろうか、、と考えたり、
僕はこう思う。と反対の意見を持ったりすることに意味があります。
この世に絶対真実というのはきっとないからです。
今日、一緒に働く17歳の子が、「世の中って、本当に大事なことを叫んでる人が偽善者扱いされたりして、なんか生きてくって難しいね。」って言ってたのを聞いて、そういう感性は大事だと思いました。批判的だったり懐疑的な部分は、苦悩も伴うけど大切だよ。
大人になると、何か疑問や違和感を感じてもうまくやりすごす術を身につけ、仕方ないと諦めることをなんとも思わなくなり、他人の不幸は対岸の火事としか思えず精神は不感症気味になっていきます。多くの大人が、です。
今週末一緒に出演する、東行さんというパンクロッカーは、多分結構いい大人なのに、世の中に真っ向からぶつかっていく感じ。数曲聴いてかっこいいと思いました。
熱いんです。それでいて、鋭いから、オモシロいんです。
熱くてクールな表現者の投げかけることは伝播していきます。
熱いだけだと馬鹿にされる割合の方が多いです。
MOROHAも竹原ピストルさんも、怖いくらいに賢いと思います。聴いたことない方は聴いてみてください。人間的には大きくてあったかい人たちだと思うけど、こういう人たちはちょっと怖さもあります。抜け目なく、真を見抜くことに長けている。
世に出る芸術家はみんなそうです。頭がよくなきゃつぶされます。
ただ社会にはむかっていくだけでは悪魔とは対峙できない、というのが僕の考えで、まず懐にもぐりこむこと。そんな器用なことを音楽や絵の術で、やってのける人たちを芸術家のひとつの定義としてます。行き過ぎると殺されたりしますけどね。。
「ゲルニカ」で有名な画家ピカソの逸話にこんなのがあります。
ナチス占領下時代のパリ、ピカソのアトリエに検閲に来たドイツ大使が「ゲルニカ」を発見して尋ねた。
「これを描いたのはあなたか。」
ピカソは答えた。
「いや違う。あなたたちだ。」
当時、ドイツ空軍による無差別爆撃によりゲルニカというスペインの小さな町で3分の1の住人が虐殺された。そのことへの怒りをピカソは絵で訴えた。

このピカソの返答はなんのひねりもない直球にも思えて、その実極上の皮肉を込めて攻撃し、しかもその場を切り抜ける打開策にもなっています。
低俗な打算ではない。冴えているんです。
21世紀最大の芸術家を例にあげて答えにこじつけるのもなんですが、
芸術家に「ぬくい」人はいません。
歌人であり劇作家でもある寺山修司はこう言いました。
「詩人にとって、言葉は凶器になることもできる。私は言葉をジャックナイフのようにひらめかせて、人の胸をぐさりとひと突きするくらいは朝飯前でなければならないな、と思った。だが同時に言葉は薬でなければならない。さまざまな心の傷手を癒すための薬に。」
それから、「マッチ擦る つかのま海に 霧深し 身捨つるほどの 祖国はありや」
という歌があります。これは太平洋戦争に敗戦した日本が復興に向かっていく時代に発表されました。そんなタイミングで虚しさを感じる寺山修司の精神の敏感さに心を打たれます。
本当、命を捨ててまで守りたい国家というのはなんだろう。今の日本は果たしてそれに値するだろうか。もちろん日本人、日本の風土や文化は守りたい。
でもみなさん、国家としての日本はどうでしょうか。
スピルバーグが憧れた映画監督、黒澤明も鋭すぎて畏怖します。
逸話がありすぎて語りきれないのでひとつを紹介。
まず、黒澤監督の作品には土砂降りの雨のシーンがよく使われる。
羅生門では、最初のカットから突然の土砂降りを見せつけ海外の人を驚かせた。
この映画をきっかけに黒澤監督は世界に名を知らしめていくのです。
これは監督がわかっていてやったんです。当時、雨のシーンを使う映画は世界にそうなかった。日本人として、そして日本映画で、世界と肩を並べるためになにをすればいいか見抜いた。その勘の良さとか、神経の敏感さは勉強ができるのとは違う思考力と直感力のなせる技です。
上にあげたようなこういう方々は他にもたくさんいるけど、人類全体としてはかなり少ない。もちろん有名でないだけでインテリジェントな人はたくさんいます。
なにが大切かに気づいていて、それを理屈でなく愛を持ってそれぞれの方法で伝えている人が。実際、僕の周りにもたくさんいます。
そしてそれらは学ぶものではなく、感得するものなんだと思います。
僕も音楽で何かを表現してく以上、「ぬくい」作品でないものも作らないと。
それが僕が音楽でやりたいことのひとつでもあるから。
「愛」と「平和」は、まず自分が感じて、体現していかないと音にならない。がんばるべ。
僕なりのやり方で「No Nukes」「No War」な世の中にすべく。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
今夜もいい夢みましょう。
P.S. 朝以降読んでくれるひとが多いと思います。なので、、、追記。
おはようございます!




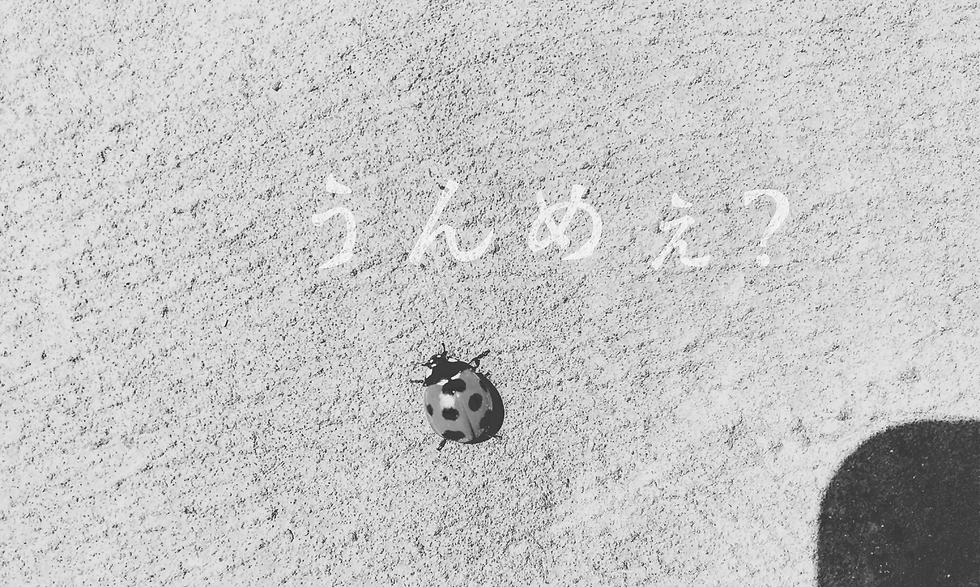
コメント